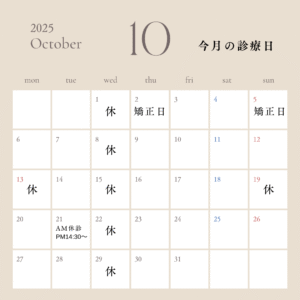あけましておめでとうございます。
藤が丘スマイル歯科の院長金子賢哉です。
年末年始は、しっかりとお休みをいただき、
家族とゆっくり過ごすことができました。
日々忙しく過ごしている中で、
こうした「立ち止まって大切な人と過ごす時間」のありがたさを改めて実感するお正月となりました。
昨年も多くの患者さまにご来院いただき、
また、スタッフ一人ひとりの支えがあって
無事に一年を終えることができました。
心より感謝申し上げます。
今年は、当院のビジョンである
「藤が丘スマイル歯科に関わるすべての人が、常に笑顔でいる。」
この言葉を、昨年以上に大切にしていきたいと考えています。
患者さまにとって
「安心して通える歯科医院」であることはもちろん
スタッフにとっても
「ここで働けてよかった」と思える場所であり続けたい。
そのために、
・丁寧な診査・診断
・納得していただける説明
・歯をできるだけ残す治療
・学び続ける姿勢
これらを一つひとつ、当たり前に、誠実に積み重ねていきます。
2026年も、
藤が丘スマイル歯科は皆さまの「笑顔」と「安心」を守るため、
スタッフ一同、真摯に診療に向き合ってまいります。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
藤が丘スマイル歯科
院長 金子賢哉
藤が丘駅から徒歩1分の歯医者|藤が丘スマイル歯科
日付: 2026年1月5日 カテゴリ:お知らせ